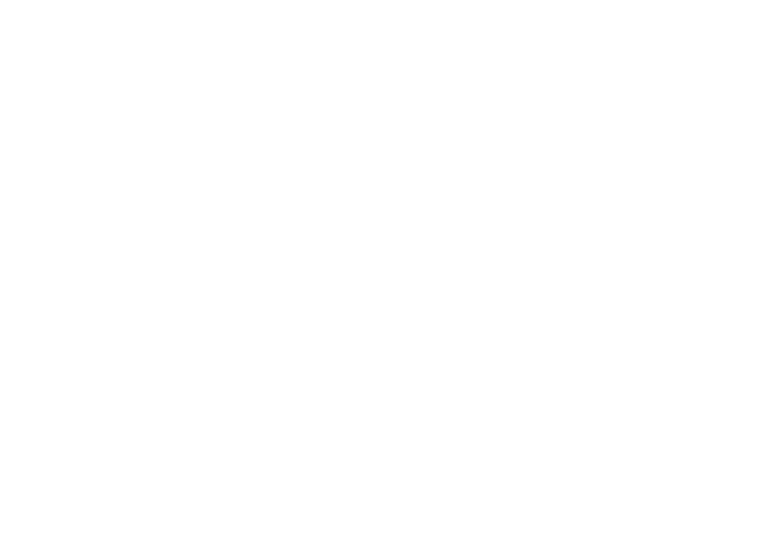Vol.24
下鴨神社の社殿
下鴨神社(賀茂神社、以下「下社」)本殿の形式を「造り」といい、上賀茂神社(賀茂神社、以下「上社」)本殿とともに、流造りを代表しています。
上社、下社の本殿は南面し、同形同大の二棟の社殿が東西に並び建っています。屋根は切妻造り、葺きで、前方にそのまま葺き下ろした屋根の流れを角柱で受けて、(神殿)の前に広い=を形成しています。向拝の下に張った床を(浜縁)といい、宮司が伺候する場となります。
神社の本殿形式には、神明造り(伊勢神宮)、大社造り(出雲大社)、八幡造り(石清水八幡宮)、日吉造り(日吉大社)などがあります。多彩な形式があるなか、流造りは、春日大社本殿に代表される春日造りとともに、広い地域に分布しています。流造りの最古の遺構は神社本殿で、平安時代後期の建築とみられています。
本殿の柱は、角材を「井」の字形に組んだ土台(井桁)の上に立っています。春日造りとも共通するこの構法は、流造りや春日造りが広く分布する背景と深く結びついているように思われます。
柱を井桁の上に立てる構法は、柱を直接地面に埋めて固定する掘立とも、また仏教建築が伝えたという礎石の上に立てるのとも異なります。それは持ち運びや移動を前提としています。臨時的、仮設的な性質を帯びているといえましょうか。古くは、カミを迎える祭壇が祭礼の都度設けられていたと考えられています。流造りと春日造りが普遍的な展開をみせるのは、遙かな昔のカミ祀りの仕方につながる構法を備えていたことが、広い共感につながったからではないでしょうか。
さて、下社の境内には、平安時代末までに幣殿、門、廻廊、舞舎(舞殿)、馬場舎、供御所等の主要な殿舎が整えられていました。鎌倉時代頃の原図に拠って室町時代に描かれた社頭古図によれば、斎院の御所や河合社の北にあった神宮寺の建築を除くほかは、現状とほとんど変わりありません。寛永五年(一六二八)に再興された殿舎の大半が現存する景観は、かつての社頭の規模や構成を踏襲して再現されています。現在の本殿は、その後、文久三年(一八六三)に造替されました。
流造りの本殿の屋根には、他の形式の本殿建築に特有なとがありません。これも流造りの特色です。柱間は正面三間(三間社流造り)、側面二間で、正面中央一間だけ板扉をたて、他はすべて板壁として身舎には縁勾(高)欄が四周しています。形式、規模ともに上社と同じです。ただし、勾欄、木階が上社では素木であるのに対して、下社では朱漆塗りです。また上社の正面両脇間に描かれた獅子、狛犬の絵が下社にはないなど、細部の手法にはわずかな差異が認められます。
幣殿の前には透塀を隔てて中門があり、左右に東西楽屋・と廊が接続して、本殿を取り囲む一連の施設が整然と配されています。
中門と楼門の間のひらけた空間には、二つの門を結ぶ軸線上に、入母屋造りの妻をそれぞれに向けて舞殿が建っています。縁勾欄が四周し柱間を吹き放した開放的な建物で、勅使の宣命を読み、東遊びが奉納されます。
舞殿の東方には細殿や御手洗川の流れの上に橋殿が架かり、西方にはを装置した住宅風な、神服を裁縫する神服殿(御服所)、神饌の調理を行う供御所等が配されています。
これらの諸殿舎が建つ一画を朱塗りの楼門と翼廊(廻廊の一部)が区切り、いにしえの山城の原生林を偲ばせる糺の森の中に、神さびた一境がつくりあげられているのです。
日向 進